こんにちは、第二種電気主任技術者のJunichi0218です。
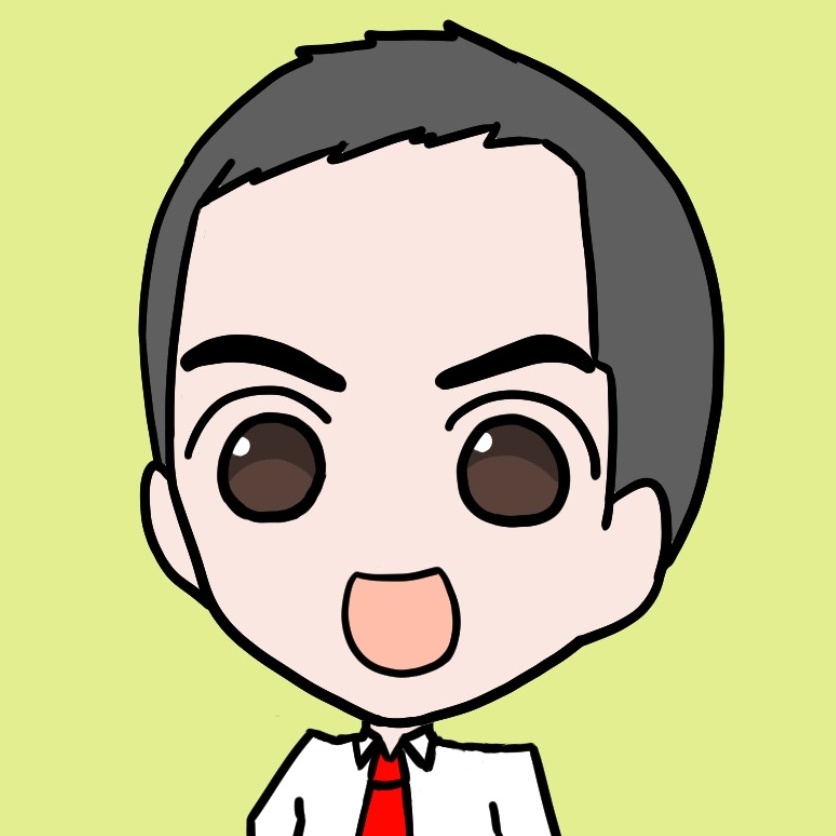
今日もよろしくお願いいたします。
今日の記事は電験二種にトライされる方向けに、私が2年前に合格後に書いた
電験二種合格体験記をさらしたいと思います。
みなさんの合格へのエッセンスに少しでもなれば幸いです。
なお、この合格体験記はオーム社の電気専門雑誌「OHM」2020年4月号に掲載されました。
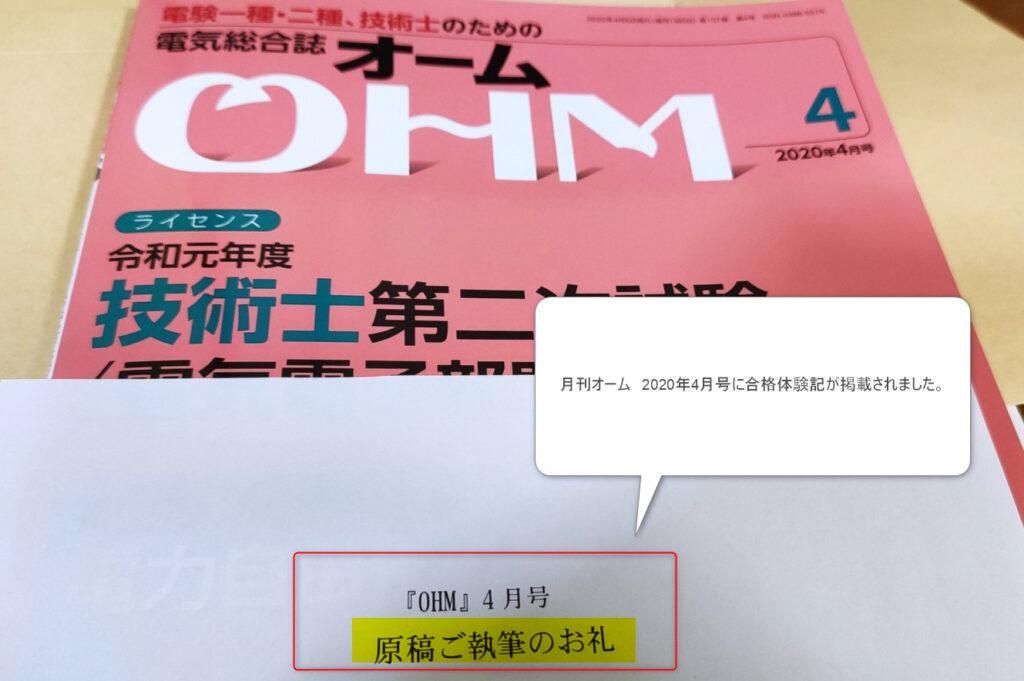

とにかく二次試験に泣かされました。2回不合格でリセット(一次試験からやりなおし)されたときはかなり悔しかったです。みなさんにはリセットの屈辱を味わってもらいたくないため、よかったら読んでください。
二回目のリセットを回避できたのが本当によかったです。
以下掲載された本文になります
受験開始から合格までのあらすじ
電験二種を五回受験しやっと合格することができました。
二次試験で三回失敗し三種のときより勉強法などかなりやりなおすことになりました。
この体験記では5年間の二種受験勉強でのやったこと・わかったことなど記したいと思います。
二種受験のきっかけ
H26年に電験三種に一発合格後、現在勤めている会社に転職し電気のことをもっと学習したいと思い、二種に挑戦することにしました。年齢も30代後半になり今しかできないと思いました。
トライ初期の主な勉強法
電験三種の学習時はE-DENの過去問DVDを主体に過去問をとにかく解いて解法を会得する勉強法だったので、二種でもE-DENのDVD通信講座や会社で申し込んだJTEX通信講座で学習し、オーム社「計算の攻略」など本屋の棚にある過去問題集をほぼすべて購入して過去問をとにかく解いて本番に臨みました。
しかしこれでは合格に不十分でした。
苦戦した1回目~4回目受験(H27~H30年度)

(画像:ODANより引用)
H27年
初受験では一次試験の理論で点数が稼げず、電力・法規の合格のみでした。
この年は特に理論の難易度が高く過渡現象が難しかったです(雑誌:電気計算講評では一種レベル)。
ほかの問題も思うように点数が稼げず不合格。
機械も知らない内容ばかりでダメでした。
二種と三種のレベルの違いを思い知らされました。
H28年
理論・機械に合格し二次試験初受験するも電力管理の点数が稼げず不合格。
この年は電力管理で計算問題4問出題されたり、機械制御も点数が稼ぎやすい誘導機・変圧器の計算問題が出題されチャンス年度だったのですが、電力管理の計算問題で思うように得点できず不合格でした。
H29年
一次試験免除で二次試験受験するが、またしても不合格。
この年は計算問題主体で一年勉強し二次試験を再度受験しましたが、電力管理が計算問題二問のみ出題。
計算問題の一問ループ電流の問題は完答できましたが、短絡容量・電圧変動率の計算問題がかなり計算ミスしました(定義がしっかり理解できてない)。論説は点数が稼げず。
さらに機械制御でも同期機・変圧器で大きな得点にならず二次試験不合格となり、一次試験から出直しとなりました。

初リセット体験。枕を涙で濡らしました。
H30年
一次試験4科目突破するもまたしても二次試験で不合格。
一次試験からやりなおしの年となったため、一次試験と二次試験の対策を平行して勉強をしました。
一次試験は4科目合格し二次試験に進むことができました。
三回目となる二次試験では電力管理では論説問題である程度得点できましたが、計算問題ではまたしても点数があまり稼げませんでした。
さらに機械制御では珍しく誘導機の論説問題が出題され、機械の論説は対策していなかったため、パワエレと自動制御と選択するもどちらも大きな点数が稼げず、この年も二次試験で不合格となりました。

さすがに勉強方法を改めないとまた二次試験で不合格になると悟り(遅いって)
勉強方法自体を考えなおし、不足しているスキルを補強しました。
勉強のやりかたを変えよう

(画像:ODANより引用)
H27~H30年の結果から三種のように過去問をひたすら解いて解法を得るやりかたでは
また不合格になると悟り、R1年の二次試験対策は以下の対策を行いました。
1、数学力アップのため高校数学やりなおし
2、電気的な事象をもっと理解するため高校物理を学習
3、ほかの職員とファミレスで勉強会を実施
4、機械制御の得点率が悪いため直流機以外の分野をとにかく練習。
5、勉強法の本を読んで勉強のしかたをリストラ
わかったこととしては数学力(三角関数・微分積分)や物理的な事象の理解が不足していたことです。
とくによかったことはYOUTUBEで家庭教師トライの数学・物理動画がすごくわかりやすく、理解が深まりました(最近の学習環境は充実してますね)。
またこれまではエビングハウスの忘却曲線に基づいて忘れる前に復讐していましたが、メンタリストDAIGOさんの本を参考に忘れかけた日に思い出すトレーニングを兼ねて復習するようにしました。
試験直前は使用テキストを不動先生の二次試験完全攻略改訂2版が発売されたため
これに切り替え、H7年以降の問題をとにかく回しました。

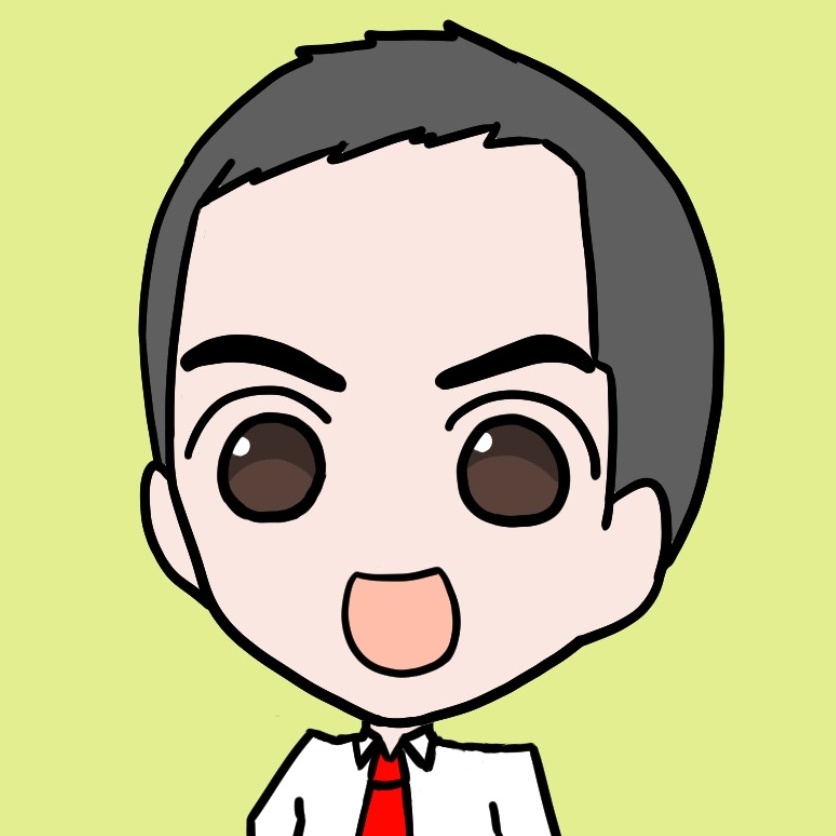
基礎的な数学力や過去問演習はとにかく全般的にやっていて深堀ができてなかったのがこれまでの主な敗因でした。
数学力の鍛えなおしや、頻出の問題を深堀理解する方向に転換しました。
勉強方法については↓の記事もご参照ください
オーム社の二次試験対策セミナーを受講

(画像はイメージです ODANより引用)
どうしても二次試験対策のヒントが欲しく、また実際に電気の生の授業をうけたことがなかったので(高校は化学工業科でしたw)東京のオーム社二次試験対策セミナー電力管理を受講しました。
講師は数々のテキストを出版されている山崎靖夫先生で、二日間の講義では先生オリジナルの予想問題を10問、制限時間を設けて模試形式で解きました(ほとんど解けなかったですが)
このセミナーで指導していただいた点は
・二次試験合格のための戦術→電力管理・機械制御とも計算問題で稼ぐ。論説は部分点狙い。電力は送配電が7~8割。
・二次試験の答案の書き方→計算問題では加点方式なので採点者に心証よく書く。また題意で与えられていない記号の定義「Vrを受電点電圧とする」や、簡易式を使用するなど解答用紙に必ず明記する。最後の答えがちょっと違っていてもたいして減点されない。論説は箇条書きでよいなど。
・練習する過去問の範囲→昭和の問題は試験方式時間配分が現在と異なるので、やるならH7以降の新制度問題を重点的にやる。
・先生の予想問題の解説が良い→後日セミナーの録音データを購入し、聞きながら何回も問題を解きました。また計算テクニックの気づきもたくさんありました。
対策し直してわかったこと
とにかく見たことがない問題に対応するためには公式の定義をしっかり理解していないとダメなことがわかりました。
また、今までの答案の書き方ではまずかったこともよくわかりました。
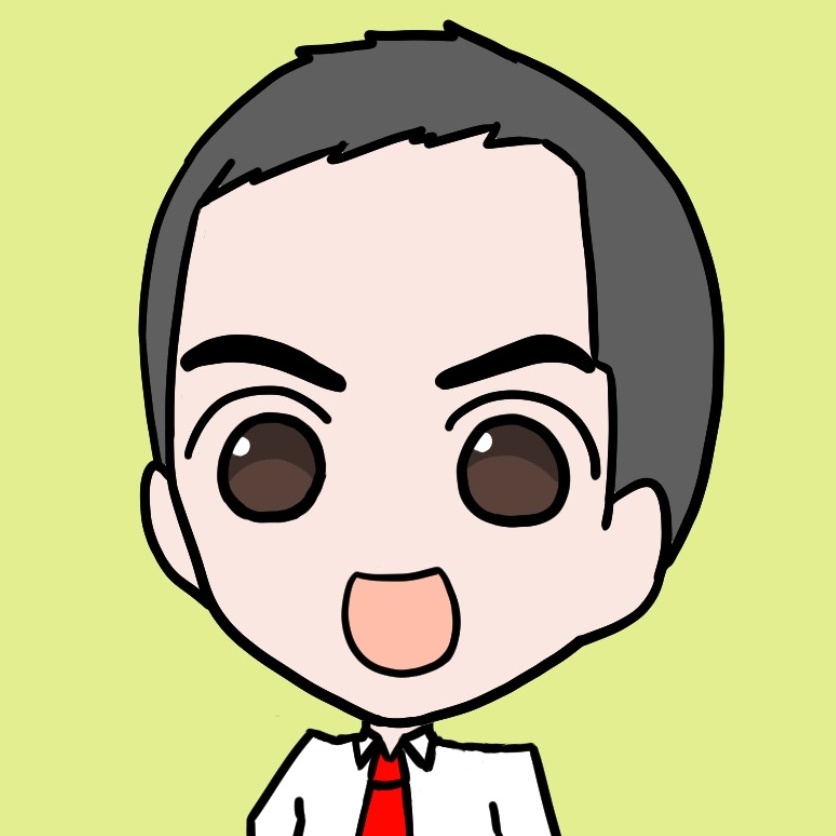
残念ながらオーム社さんのセミナーはコロナで休講となっております(2021年10月現在)
また開講してほしいですね!
そして迎えた5回目の試験(R1年試験)

(画像:ODANより引用)
対策をしなおして四回目の二次試験を受験です。
電力管理では問2・問4・問5・問6を選択し、自己採点では55~60点ほど稼げた感触でした。
機械制御では誘導機と変圧器を選択、変圧器はセミナーの予想問題そっくりな問題が出題!
30分で二問とも解き、残りの30分は見直しにあてました。終わった直後の感触では二問完答で60点稼げたと思いました。
しかし数日後解きなおしたら計算間違いしていることに気づき機械制御は35~45点の採点となりました。
二科目あわせて自己採点90~105点と調整が入れば合格に届く結果となりました。
ついに合格発表日
R2年2月5日ついに合格発表です。
会社でいっしょに受験した若手職員(この方は先に合格を確認しました)が見守る中、自席のパソコンに向かい受験番号を入力!
マウスも持つ手が緊張で震えガタガタしました。モニタに現れた結果は
「入力した番号は合格者一覧にあります」でした!
ついに合格です!
信じられませんでした!
プレスリリースを確認したところ二次試験合格点は総合108点・二科目平均点調整なしで二次試験合格率は23%でした(私の受験した北陸では18%でした)
合格者数が例年より多く、かなりの当たり年だったようですが、とにかく合格でこれまでの苦労が報われ涙が出そうになりました。

自己採点では60%の108点に届いてはいないと思っていましたが、セミナーで言ってた加点採点方式なのか記述した計算式に点数が結構付いて108点に届いたのかもしれません(確認はできませんが)
とにかく合格できてほっとしました。
これから二種を受ける方へ
まず公式暗記はよくないです。公式がどうして成り立っているか定義を時間をかけてでも理解するのが近道かと思います。
また過去問をまわすのがやはり重要で、特に二次試験の過去問題は解法がわかれば15分ぐらいで解けるように電卓をたたいて練習するべきかと思います。
私は試験直前には簡単な計算問題は紙に書かないで頭の中で式を立て、電卓だけで解けるようにトレーニングもしました。
またテキストによって問題の解き方がちがう場合があるので、自分に合う解き方を取り入れ、マスターするのもいいと思います。
そしてインプット(定義・基礎を抑える)とアウトプット(解き方を思い出す、計算の仕方など練習)のバランスを意識するのがいいと思います。
二次試験の書き方については以下の記事を参照ください
そしてこれから
実はR1年に一種の一次試験をまた受け、電力と機械に合格しました。
今後は一種目指して学習し、一種合格後(何年かかるかわかりませんが)は技術士二次試験の電気設備部門を受験したいと考えてます。
将来的には技術者として講演や電験指導で稼げるよう自己研鑽していきたいと思います。
おわり

最後までありがとうございました。今年R5年は電験一種二次試験(二回目)に向けて学習中です。
栄えある合格を勝ちとれるのかわかりませんが、頑張ってみたいと思います。みなさんも是非頑張ってくださいね!
本記事は以上です。またよろしくお願いいたします!
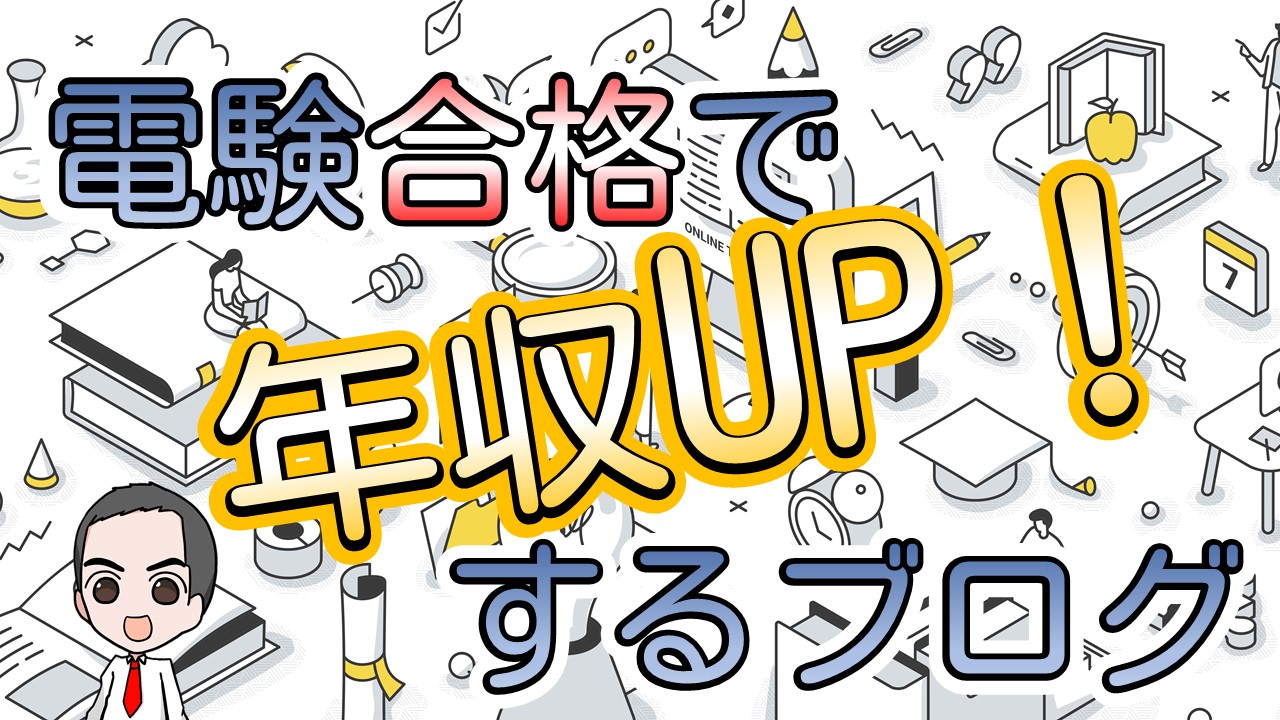
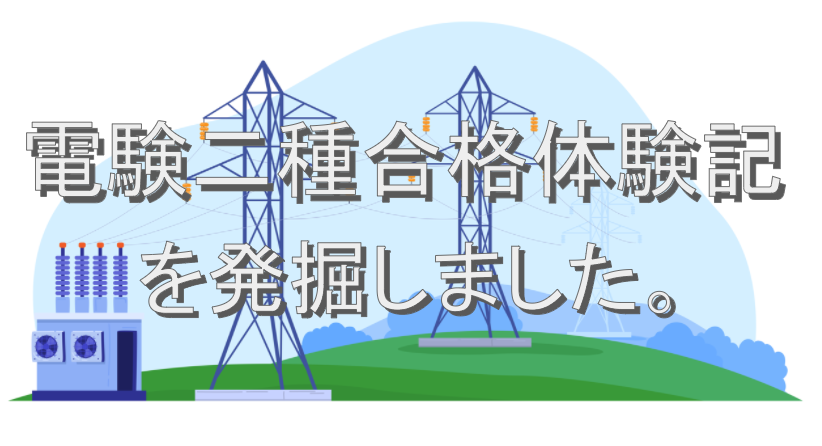

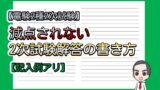


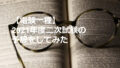
コメント